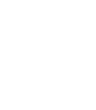2024年4月の記事一覧
階段下の有効活用
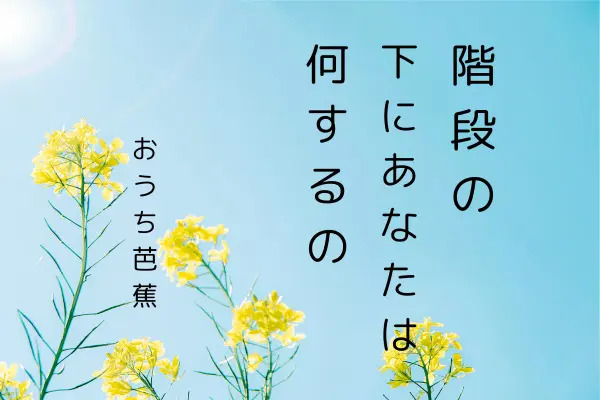
階段下はデットスペースになりがちで悩みますよね・・・
「無難に収納にしておくか・・・」
って思っているそこのあなた!!!
収納以外にも色々と使い道がございます!
今回は、弊社のお客様で階段下をどのように活用したかをご紹介いたします!
※間取りによって変わりますので参考程度に
①収納スペース
一番多いのが「収納スペース」ですね!
最近は扉などを付け、見えない収納をする方が多いようです。
稼働棚で収納ボックスを使用し整理整頓された収納スペースは、
見た目も美しく使い勝手も良くなりますね!
②トイレ
階段下にトイレを設置することでトイレのスペースを確保しなくてもよく、
他に有効活用することができますね!
「LDKをもう少し広げたい」
「玄関をもっと広げたい」
など検討されている方に良いかもですね!
③パントリー
食品やキッチン用品などを収納するパントリー!
パントリーを導入したい奥様方が多いですよね!
「予算的にパントリーが作れない・・・」など悩まれている方は
間取の配置によりますが、階段下にパントリーの設置も検討してはいかがですか?
④ソファーを置く
リビング階段のお客様で地味に多かったのが
この「ソファーを置く」です!
どうしてもソファーを置くとLDKのスペースが取られてしまい
LDKが狭く感じてしまいます。ただでさえ階段もありますからね・・・
そこで、階段下にソファーを置くことでLDKを広々と使うことができますね!
近年LDKの大きさは小さくなってきているので、
ナイス(アイディア)ですねぇ~
⑤キッズスペース
リビング階段導入で既にお子様がいる方に多いのが
「キッズスペース」
お子様がいる方にはわかると思いますが、
どうしてもおもちゃが散らかりますよね・・・
来客も考えるとリビングにおもちゃを散らかしたくはないです!
階段下にキッズスペース設けることで
目の届く範囲でお子様を遊ばせることもでき、
おもちゃも片付けられるので常にLDKは綺麗に保てそうですね!
⑥インテリアを置く
導入されているお客様は少ないですがご紹介します。
空間のアクセントとなるインテリアを置くことで
お部屋のセンスがレベルアップします!
インテリア好きの家庭はぜひ導入の検討を!
⑦ワークスペース(スタディースペース)
最近はリモートワークも多くなってきており、
書斎やワークスペースを設ける方も多くなってきています。
階段下ですので広々している訳でもなく、程よいスペース感となっています!
仕事するにも丁度良い大きさ、将来お子さんのスタディースペースにも活用できますね!
⑧ヌック
階段下をヌックにすることで、おこもり空間を演出できます!
同じ空間にいながらテレビを見ている人がいたり、読書をしている人がいたりと、
各々が別のことをして過ごしながらもほどよい距離感でつながる空間にしたいという場合は、
ヌックはとても有効です!!!
楽しいときもつらいときも、家ではいろいろな感情とともに暮らしますが、
ヌックをプラスしていろいろな「居場所」をつくることで、住まいの居心地はグンと上がります。
どうでしたか?参考になりましたでしょうか?
階段下の有効活用で家の雰囲気はガラッと変わってきます!
こんな相談もKURASU SAPPORT秋田でしてみませんか?
第三者目線でいろいろお伝えいたします!
ご予約お待ちしております!
理想の土地を探すには

住宅購入を考える際に重要なこと
それは「どこに」おうちを建てるか
現在住んでいるところの近く
お子さまの学区
実家に近いところ
生活環境の良いところ
「どこ」を選ぶかの基準は人それぞれ
絶対この地区じゃなきゃダメ
できればこの辺りがいいな
住宅購入の様々な選択肢のなかで「どこ」の優先順位の高さも人それぞれです
「どこ」を絞り込めば絞り込むほど土地探しは難しくなります
購入を早く進めたい場合は許容範囲を広げることも一つの手段ですが
一度購入したら二度目の購入は難しいのがおうち
「どこ」も含めて後悔の無いおうち作りのお手伝いがしたいです
土地を探すには
①売りに出ているものの中から選ぶ
②住宅業者さんと一緒に探してもらう
③自分の足で探す
①は多くの方が目にする情報ですので他にその土地が欲しい方がいると競合し先着順になる場合もあります
先着順とは問い合わせをした順番ではなく正式に申し込みをした順番
ですが…
順番は売主さんの意向で変更ができます
例えば支払時期が早いお客さまを優先する場合など
もちろん現金払いができるお客さまは支払いが早いですが
住宅ローンを使う場合でもすでに審査が通っている方は有利です
まだ審査もしていない…
建物を建てる住宅業者も決まっていない…
という段階だと
「そこまで真剣ではないのかな…」
などと思われてしまう場合もありますのでご注意ください
土地の探し方②と③については次回以降のコラムでお話をさせていただきます
先ほども言いました通り
私たちはお客さまの後悔しないおうち作りのお手伝いがしたいです!
「どこ」探しはおうち作りの大事な一歩
ぜひご相談ください
秋田キッズマネースクール【4月21日開催】
4月のキッズマネースクールの開催が決定いたしましたのでお知らせします!!

今回は新コンテンツ!
「おかいもの大作戦~みんなはお金をどう使う?~」
お買い物体験をすることで、お金や物の価値、誰かのために行動すること、お店の人とのコミュニケーションが学べます!
お子さんだけのおつかいをはじめるきっかけとして、親子で予行練習してみませんか?
すでに経験のあるお子さんでも、もちろんオッケーです!
楽しく学べて、最後は感動できるコンテンツです!!
コンテンツ
親子で楽しく「お金について」を学べる体験型プラグラム
お子さんはお買い物(おつかい)に行ったことはあるますか?
このコンテンツではクイズや劇でお金について学んだり、お買い物の疑似体験ができます。
親御さんはお子様の年齢に合わせて「ごはんの材料」の指令を出し、
子どもたちは途中で起こる様々な誘惑に対応しながら
お買い物をしてもらう子どもの自立を支援するプログラムです。
また「お金の大切さ」や「家族の一員としてどんな協力ができるか」を学ぶこともできます。
子ども達がお買い物に使うバッグ工作をしている間は、
おうちの方に向けた講座を開催。
・これからの子どもの職業について
・おこづかいについて
など様々なコンテンツを用意しております。
【当日の流れ】
1.クイズで学ぼう!お金や物の価格の歴史
まずはお金の歴史をクイズで学ぼう!
お金の種類についてやいつも買っているものの値段が昔とどう違うのかを知ることができるよ。
2.劇で知ろう!おかいものってどうするの?
赤ずきんちゃんがお母さんから頼まれたものを買いにお店へ。
だけどそこにはオオカミが現れて…
赤ずきんちゃんは無事におかいものできるかな?
3.おかいものの準備をしよう!
オリジナルのおかいものバッグを作っておかいものへ行く準備をしよう。
親御さんへは、お金の専門家によるセミナーを開催。
4.おかいものを体験してみよう!
自分たちで作ったおかいものバッグを持っておうちの方に頼まれたごはんの材料をかってみよう!
オオカミの誘惑に負けずに買って帰れるかな?
日時
4月21日 日曜日
10:00 ~ 12:00
受付開始は15分前です。
場所
さきがけホール
〒010-0956 秋田市山王臨海町1-1 秋田魁新報社1階
対象
4歳から8歳のお子さまとその保護者さま
持ち物
色えんぴつ
定員
先着15組
講師(予定)
・岡本 たくま せんせい
・大野 くみこ せんせい
・小林 みお せんせい
お申込みページ
LINEでのお申込みとなります。
下記より、LINE友だち登録の上、お申込みください!
親からの支援~住宅購入~

みなさんこんにちは。
4月からまた資材高騰などにより、住宅購入の費用も今までよりも負担が大きくなることが予想されます。
中には親からの支援を必要とする人もいるかもしれませんが、それって問題ないの?と気になる方もいるのではないでしょうか。
今日はその点についてお話していきます。
親からの支援を受ける際に活用できる特例や制度
親からの支援を受けて住宅を購入する際には、以下の特例や制度を活用できます。
- 住宅取得資金贈与の非課税の特例
- 相続時精算課税制度
- 歴年課税制度
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
住宅取得資金贈与の非課税の特例
これは住宅新築や購入などの目的で直径尊属(父母や祖父母など)から資金贈与を受けた際に、非課税枠を利用することが可能です。
【金額】
・省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅 ⇒ 1,000万円
・上記以外の住宅 ⇒ 500万円
【要件】
・贈与を受けた1月1日時点で18歳以上
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
(床面積が40平方メートル以上 50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得資金の全額を充てて、
住宅用の家屋の新築・取得などをする
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、新築・取得などをした家屋に居住する
(または居住することが確実であると見込まれる)
などがあります。より詳しい内容については国税庁のHPをご覧ください。
相続時精算課税制度
これは60歳以上の父母または祖父母から受けた贈与について、通算で2,500万円(特別控除額)までは贈与税が課されない仕組みです。2,500万円を超える部分については、一律20%の税率が課税されます。
この制度を利用することで、2,500万円までは親からの支援を非課税で受けることが可能となります。
ただし、以下の点について注意が必要です。
【注意点】
・贈与を受ける側が18歳以上であること。
・最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署への手続きを行う必要がある。
・相続時精算課税制度を使った間柄の贈与は二度と暦年贈与制度を使えない。
・贈与をした父母・祖父母が亡くなった時点で、今回贈与した金額と相続財産の金額が合計されて
相続税を計算される。
などがあげられます。
暦年課税制度
②の相続時精算課税制度が適用されていない場合の贈与については、暦年課税制度が適用されます。
この場合、年間110万円(基礎控除額)までは贈与税がかかりません。
この110万円を超える場合には贈与税が加算されます。
こちらについても国税庁のHOなどをご覧ください。
まとめ
このように、親からの支援を受ける際には活用できる制度があります。これらをうまく活用すると良いでしょう。ただし、申告がしっかりと必要になります。申告や納付をせずにいると、後日税務署から税務調査を受け、無申告加算税を払うことになるかもしれませんのでご注意ください。